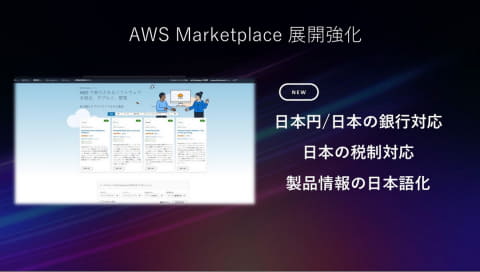ニュース
AWSジャパンの2025年パートナー戦略、生成AIやクラウド移行などに注力
2025年5月9日 10:00
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下、AWSジャパン)は8日、2025年のパートナー戦略について説明会を開催し、AWSジャパン パートナーアライアンス事業統括本部 常務執行役員 事業統括本部長の渡邉宗行氏が「今年は生成AI、マイグレーション・モダナイゼーション、AWS Marketplace、人材育成の4分野に注力する」と述べた。
注力分野1:生成AI
まず生成AIについて渡邉氏は、AWSの生成AIスタックを構成する3つの層を紹介した。ベースとなるのが、AIモデルを構築し学習させるためのインフラストラクチャで、この層ではマネージドインフラの「Amazon SageMaker AI」や、ハイパフォーマンスなコンピュートリソースとなる「AWS Trainium」「AWS Inferentia」などを用意している。その上の層では、生成AIアプリケーションを構築するモデルとして「Amazon Bedrock」を提供し、最もユーザーに近いアプリケーション層では、ビジネスを支援する「Amazon Q Business」、開発を支援する「Amazon Q Developer」を提供している。
Amazon Bedrockでは、現在9つの基盤モデルが選択できるようになっている。「Amazon Nova」はもちろんのこと、AI21 Labsの「Jamba」や、Anthropicの「Claude」、Metaの「Llama」などもその中に含まれており、「マネージドサービスにて同一APIで提供することが特徴だ」と渡邉氏は説明する。
2024年には、AWSを活用した生成AIの高度なスキルを持つパートナーを認定する「生成AIコンピテンシー」というプログラムも開始した。日本では、株式会社野村総合研究所とアイレット株式会社がすでに認定を取得しているという。2025年は、「より多くのパートナー企業に認定を取得してもらい、専門性の指標とする。そのための技術支援を実施する」としている。
AWSでは、生成AIを「ビジネスのための生成AI」と「生産性向上のための生成AI」に分類している。ビジネスのための生成AIでは、パートナー企業のビジネス拡大を支援する。事例としては、NTTデータがAmazon Bedrock Agentを活用した営業活動の高度化を支えるエージェントサービスを提供しているほか、日立製作所が「JP1 Cloud Service」の生成AIアシスタントにAmazon Bedrockを採用しているという。
一方の生産性向上のための生成AIでは、開発と運用の効率化を促進する。具体的には、Amazon Q Developerでシステムの設計や開発、テスト、運用のすべてを支援し、生産性向上とコスト削減を実現するという。
渡邉氏は、「去年まで生成AIはPoCばかりだと言われていたが、すでにその段階は終わった。生成AIはすでにビジネスの中心に組み込まれており、利用の有無が競争力の差につながるため、パートナー企業にも積極的に生成AIを活用してもらいたい」とした。
注力分野2:マイグレーション・モダナイゼーション
マイグレーション・モダナイゼーションに関しては、クラウド移行を総合的に支援する「ITトランスフォーメーションパッケージ(ITX)」を用意している。このパッケージは、既存のシステム資産を効率的かつ最適なコストでAWSクラウドへ移行し、その後のアーキテクチャ最新化までを総合的に支援するもので、「移行前のアセスメントや意思決定支援、移行パターンの策定、実施、運用といったプロセスをパッケージとして提供する」と渡邉氏は説明する。
また、移行支援体制として、マイグレーションに強みを持つパートナーに「マイグレーション&モダナイゼーションコンピテンシー」を認定。これらのパートナーがITXパッケージを活用することで、顧客にシームレスな移行提案ができるよう体制を整えているという。
具体的な事例として渡邉氏は、沖電気工業株式会社のクラウド移行プロジェクトを紹介。同社は2025年までに自社データセンターを閉鎖し、約300システムをAWSへ移行する計画を立て、その移行をパートナーのSCSK株式会社がITXパッケージを活用して支援した。SCSKは、自社クラウドサービスも組み合わせることで、当初の予定よりも早い移行を実現したという。
渡邉氏は、「今後さらに多くのパートナーにITXパッケージを活用してもらい、顧客のクラウド移行を推進したい」と述べており、特に今年は「メインフレームからAWSへの移行や、仮想化基盤の見直しが進むVMware環境の移行、ECC6.0のサポート修了が2027年に迫るSAPからの移行、.NETのリファクタリングによるライセンスコスト削減に注力する」としている。
注力分野3:AWS Marketplace
AWS Marketplaceについて渡邉氏は、「顧客とパートナー企業を結ぶデジタルカタログとなっており、AWS上で利用可能なサードパーティーソフトウェアを簡単に検索し、購入して導入できる」と説明する。「このシステムにより、顧客は幅広い製品から選択できるだけでなく、AWSの利用と同じ請求システムでソフトウェアが調達できる。また、セキュリティとガバナンスを強化し、コストの最適化も可能だ」と渡邉氏はアピールする。
具体例として渡邉氏は、株式会社保健同人フロンティアが、AWS Marketplaceを通じて脆弱性管理ツール「yamory」を導入したことで、セキュリティ強化と手続きの簡素化を達成したと紹介。また、ディップ株式会社は6つのISVパートナーのソリューション調達をAWS Marketplaceに集約し、調達コストの透明化と管理の一元化を実施したという。
日本市場向けには、2023年10月に日本円の対応と日本の銀行での取引が可能になり、2024年4月には日本の税制にも対応した。さらに、2024年5月には製品情報の日本語化が完了し、日本の顧客がサービス内容を適切に理解できる環境が整った。
こうした状況を受け、今後AWSジャパンでは、日本のISVやSI企業がMarketplaceに参加しやすくなるよう技術支援やビジネスプランニングのサポートを強化するという。また、AWSとパートナー企業による共同販売や提案活動を加速させ、個別見積もりなどを含めた日本市場に最適なモデルを構築する。さらには、ISVとSIのマッチングを推進し、日本の顧客が最適なソリューションを選択し導入できる環境を整えるという。
注力分野4:人材育成
人材育成を重視する背景について渡邉氏は、「パートナー企業のスキル向上なしには日本のクラウド普及は進まない」と主張する。近年ではクラウド関連スキルのニーズが、インフラエンジニアからアプリケーションエンジニアやAI、データ、セキュリティ分野へと広がり、より専門的で深いトレーニングが求められるようになっているという。
こうした状況を受け、AWSはAI Practitioner認定資格など新たな認定制度を導入したほか、グローバル共通コンテンツと日本独自の実践的なトレーニングを組み合わせたトレーニングマップを構築し、日本市場に適したトレーニングを充実させている。デジタルトレーニングプラットフォーム「AWS Skill Builder」では、600以上のコンテンツを用意、日本国内のあらゆる地域に効率的にトレーニングを届けることを目指す。
また、企業の内製化支援にも注力しており、パートナーと協力して「内製化支援推進AWSパートナー」制度を展開。2021年の開始当初10社だった参加企業は、2025年には42社に拡大し、生成AI活用支援サービスなど新たな取り組みも始まっているという。
渡邉氏は、「パートナーとともに、今後も人材育成と内製化支援を強化する。こうした取り組みを通じ、あらゆる業種・地域・規模の企業にクラウドのメリットを届け、企業の体質強化とビジネス成長に貢献したい」としている。